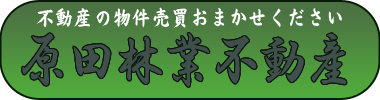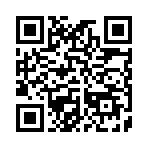2016年01月24日
先人の遺構
河浦町矢筈岳の作業現場です。
天然林の伐採途中に,先人の遺構を発見しました。
標高約400m,麓(ふもと)の人家から約5km。
おそらく,焼畑などの石積みではないかと思われます。
昔はここで,何を栽培されていたのでしょうか。
こちらは,炭焼きの窯跡です。
私が生まれる40年数年程前までは,木炭(もくたん)が燃料の主役だったと聞いています。
いずれにしても,機械などの動力はなく,人力や牛馬での作業時代の遺構を目にして,先人の方々の苦労に
何ともいえない感慨を覚え,ただ,ただ、頭が下がります。
効率先行の今の世代に対して,静かに何かを語りかけているような気がします。
comment:(0) category:林業category:その他
2016年01月20日
雪の足跡
今日の新和町大宮地平家城山の山頂です。
「 雪の朝 二の字二の字の 下駄の跡 」ならぬ,「いのしし二頭分」の足跡がありました。
この雪の中,彼らも必死にえさを探しているのでしょう。
「いのしし」に負けじと,雪をかき分けながら測量を行いましたが,あまりさばけませんでした。
今週末も雪の予報が出ていますが,もう勘弁して欲しいものです。
2016年01月19日
吹雪でした
新和町大宮地の平家城山の山頂です。標高約317メートル。
麓(ふもと)はみぞれがパラパラでしたので大丈夫だろうと思いつつ登ってみると,中腹付近から粉雪に変わり,山頂は吹雪となりました。
南国天草とはいえ,さすがに標高の高い場所は雪がすごかですね。
積雪約15cm。帰路のことも考え,本日の作業はやむなく中止としました。
2016年01月18日
泥壁
最近は泥壁の家を見かけなくなりました。
泥壁には,赤土に藁(わら)をまぜ充分に発酵させ(ねまらせ)たものを使用します。
竹小舞をえつり中
竹小舞完成
作業員総出で一気に塗り上げ
外部は漆喰で仕上げ
内部も漆喰で統一,左官職人の技が光ります。
泥壁には,「あたたまりにくく冷めにくい」蓄熱・蓄冷効果や,湿度をコントロールする調湿効果があり,
冬あたたかく夏すずしい暮らしをつくります。
時間と手間がかかる品物ですが,自然素材を生かした家づくり,いかがでしょうか。
comment:(0) category:林業category:不動産
2016年01月14日
天草の木その3
天草の木材を使用した住宅を紹介します。
今回は,楠(クス)材の部分の一例です。

左上から右下に向かって3本が楠(クス)。宮地岳の山林に自生していたもの(樹齢約90年,長さ約30m)を伐採,2間(約4m)に玉切って搬出。

元玉(一番根元から木取りした部分)の末口(直径)約54cm。

上の写真の原木が階段の手摺りや踏み板に生まれ変わりました。

木目(もくめ)が美しいです。
住宅の建材は,杉(スギ)や桧(ヒノキ)などの針葉樹が中心ですが,楠(クス)などの広葉樹もアクセント的に取り入れることで,従来の家とはまた違った空間が楽しめます。
今回は,楠(クス)材の部分の一例です。
左上から右下に向かって3本が楠(クス)。宮地岳の山林に自生していたもの(樹齢約90年,長さ約30m)を伐採,2間(約4m)に玉切って搬出。
元玉(一番根元から木取りした部分)の末口(直径)約54cm。
上の写真の原木が階段の手摺りや踏み板に生まれ変わりました。
木目(もくめ)が美しいです。
住宅の建材は,杉(スギ)や桧(ヒノキ)などの針葉樹が中心ですが,楠(クス)などの広葉樹もアクセント的に取り入れることで,従来の家とはまた違った空間が楽しめます。
comment:(0) category:林業category:不動産
2016年01月08日
天草の木その2
天草の木材を使用した住宅を紹介します。
今回は,桧(ヒノキ)材の部分の一例です。

本柱(ほんばしら): 7寸(約21cm)角の大黒柱です。家の中心部にあり,梁(はり)や桁(けた),胴差(どうざし)などの横架材を支えます。節(ふし)の少ないきれいな材が取れました。

縁甲板(えんこいた): 4寸(約12cm)幅×5分(約1.5cm)厚のフローリングです。玄関から続く縁側に無節(むぶし)を張ってあります。

これも桧(ヒノキ)のフローリングです。節(ふし)ありですが,木の表情を楽しめ,個人的にはこちらの方が好きです。

外部板(がいぶいた): 5寸(約15cm)幅×5分(約1.5cm)厚です。外回りのため塗装してあります。

軒天板(のきてんいた): 3,5寸(約10.5cm)幅×4分(約1.2cm)厚です。これも塗装してあります。
この他,主なところでは基礎部分の土台(どだい)に桧(ヒノキ)を使用しています。
天草の木は,自生している山の土壌が痩せているため成長が遅く,その分目が詰まり艶(つや)があり,確かな強度を持っています。
これは大工さんから聞いた話ですが,天草の木か他所の木かの違いは,鑿(のみ)を入れた時の木の固さですぐに分かるそうです。
天草の人が家を造る際,他所の地域の木でなく,地元の木をもっと活用していただければと願っています。
今回は,桧(ヒノキ)材の部分の一例です。
本柱(ほんばしら): 7寸(約21cm)角の大黒柱です。家の中心部にあり,梁(はり)や桁(けた),胴差(どうざし)などの横架材を支えます。節(ふし)の少ないきれいな材が取れました。
縁甲板(えんこいた): 4寸(約12cm)幅×5分(約1.5cm)厚のフローリングです。玄関から続く縁側に無節(むぶし)を張ってあります。
これも桧(ヒノキ)のフローリングです。節(ふし)ありですが,木の表情を楽しめ,個人的にはこちらの方が好きです。
外部板(がいぶいた): 5寸(約15cm)幅×5分(約1.5cm)厚です。外回りのため塗装してあります。
軒天板(のきてんいた): 3,5寸(約10.5cm)幅×4分(約1.2cm)厚です。これも塗装してあります。
この他,主なところでは基礎部分の土台(どだい)に桧(ヒノキ)を使用しています。
天草の木は,自生している山の土壌が痩せているため成長が遅く,その分目が詰まり艶(つや)があり,確かな強度を持っています。
これは大工さんから聞いた話ですが,天草の木か他所の木かの違いは,鑿(のみ)を入れた時の木の固さですぐに分かるそうです。
天草の人が家を造る際,他所の地域の木でなく,地元の木をもっと活用していただければと願っています。
comment:(2) category:林業category:不動産
2016年01月06日
天草の木その1
天草の木材を使用した住宅を紹介します。
今回は,杉(スギ)材の部分の一例です。

梁(はり),桁(けた): 小屋組みの部分です。梁は釿(ちょうな)ではつってあり,釘を使用せず込み栓を打ち込んであります。
一番上の梁を空梁(くうりょう)といい,家の重心を安定させるものです。

胴差(どうざし): 横架材です。尺2寸(約36センチ)×5寸(約15cm)×14尺5寸(約4m35cm)。吹き抜けのため化粧仕上げにしており,艶(つや)が出ています。もちろん塗装はしていません。

天井板(てんじょういた): 樹齢120年の杉から木取りしています。尺3寸(約39センチ)×3分(約0.9cm)×2間(約4m)。若干,節(ふし)が出ましたがこれもご愛嬌。

腰板(こしいた): これも高樹齢材の根元部分から木取りしています。表情が色々あり楽しいです。

建具(写真は引き戸)も全て杉で造っています。
昔から,天草の杉(スギ)はねばりがと強度があるため,日本中の船材(せんざい)にひっぱりだこだったそうです。
現在はその特性を利用して,住宅の梁(はり)や桁(けた)といった強度を求められる部分に活用したり,また,高樹齢のものは化粧板に活用したりしています。
これから少しづつ,天草の木材の使用例をUPしていきますので,どうかお付き合いください。
今回は,杉(スギ)材の部分の一例です。
梁(はり),桁(けた): 小屋組みの部分です。梁は釿(ちょうな)ではつってあり,釘を使用せず込み栓を打ち込んであります。
一番上の梁を空梁(くうりょう)といい,家の重心を安定させるものです。
胴差(どうざし): 横架材です。尺2寸(約36センチ)×5寸(約15cm)×14尺5寸(約4m35cm)。吹き抜けのため化粧仕上げにしており,艶(つや)が出ています。もちろん塗装はしていません。
天井板(てんじょういた): 樹齢120年の杉から木取りしています。尺3寸(約39センチ)×3分(約0.9cm)×2間(約4m)。若干,節(ふし)が出ましたがこれもご愛嬌。
腰板(こしいた): これも高樹齢材の根元部分から木取りしています。表情が色々あり楽しいです。
建具(写真は引き戸)も全て杉で造っています。
昔から,天草の杉(スギ)はねばりがと強度があるため,日本中の船材(せんざい)にひっぱりだこだったそうです。
現在はその特性を利用して,住宅の梁(はり)や桁(けた)といった強度を求められる部分に活用したり,また,高樹齢のものは化粧板に活用したりしています。
これから少しづつ,天草の木材の使用例をUPしていきますので,どうかお付き合いください。
comment:(2) category:林業category:不動産
2016年01月04日
仕事始め
あけましておめでとうございます。
今日から仕事始めとなりました。
といっても,現場作業は7日(木)からのため

地元の神社にて今年一年の安全作業を祈願

年末できなかった(というか溜めていた)事務処理をやっつけ

チェンソーを分解して掃除したり(これも年末にやっておくべきことですが・・・)と,
7日(木)の現場作業開始に向けてスタンバイ中です。
今年もよろしくお願いします。
今日から仕事始めとなりました。
といっても,現場作業は7日(木)からのため
地元の神社にて今年一年の安全作業を祈願
年末できなかった(というか溜めていた)事務処理をやっつけ
チェンソーを分解して掃除したり(これも年末にやっておくべきことですが・・・)と,
7日(木)の現場作業開始に向けてスタンバイ中です。
今年もよろしくお願いします。
2015年12月23日
牛深節
牛深節です。(ハイヤではありません)
牛深地区は,江戸時代からカツオ節以外の削り節(雑節)の生産が盛んで,その生産量は日本一とのこと。
(ムロアジの節)
(ウルメイワシの節)
(従業員総出の作業)
(燻製室)
(燻製用の薪 ※写真の薪は弊社の山林から伐採したものです)
(薪をくべて燻し中 ※くどいようですが弊社の薪です,よく燃えます)
(完成したソウダカツオの節)
牛深節は,主に天草近海で水揚げされたサバ,ムロアジ,ウルメイワシなどを原料とし,関西方面へうどん,ラーメン,
おでんなどの「だし」として,または,大手食品メーカーの調味料(麺つゆ等)の原料として出荷するそうです。
最近は,「和食;日本人の伝統的な食文化 」がユネスコ 無形文化遺産に登録され ,和食の基本である「だし」が注目
されています。
牛深節が世界遺産である和食の「だし」に貢献していることを,もっと注目されてもいいのではないでしょうか。
comment:(0) category:林業category:その他